会社が倒産するときは、利益が出なくなったときではなく、キャッシュが底をついたときである。どんな良いサービスを提供しても、持続しなければ悲しい。持続性を意識して、自社では5つのことを意識している。結論から言うと、①コツコツ黒字を積み上げて、②実質無借金経営でB/Sを厚くすることを意識しながら、③内部留保をためて、④自己資本比率を50%以上を目標にし、⑤持続可能な会社を追求することである。
黒字体質
まだ3期の決算しか終了していない会社ではあるが、3期連続の黒字である。(独立後の個人事業の2年は悲惨だった笑)小さい会社の戦い方をしていこうと思っている。少なくてもいいから、黒字にして純資産を積み上げる。赤字だとしても戦略的な赤字にしないと意味がない。黒字は癖である。
経常利益が上がると、節税したくなるのは、それはもっともだし、必要な節税はすべきだと思う。だけど、節税を目的に何かをしてはいけない。節税は結果であって、それを目的にすると結局はキャッシュが出ていき弱い会社になる。例えば、パソコンが壊れて、新調して結果として税金が安くなった。とかはgoodである。
自己資本比率が低い中で保険で節税とか愚の骨頂である。
実質無借金経営
実質無借金経営とは、現金>借入金の状況である。もちろん借金がないにこしたことはないが、初期の段階で借金をせずにビジネスを行うのは難しいし、借金をせずにB/Sが薄い会社も弱い。
例えば、Aさん:現金1億で借金1億。Bさん:現金0円、借金0円。どちらも純資産(資産-負債)は0円であり、同じ状況である。借金をただ怖いという人は、Bさんを選択するかもしれないが、圧倒的にAさんの方が、会社を強くするには、B/Sを厚くすることだ。Aさんは何度もチャレンジできる状況である。
ただし、Aさんもいくらキャッシュがあったとしてもそれは借金である。いつか返していかないといけないお金である。そこで重要なのが、借金は「利益の前借」という意識である。借金は利益を先にもらってるだけであるので、慎重に使わないといけない。当たり前だが、結構ビジネス初期では借金の管理を怠ってしまう。起業する人はそもそもでリスクの許容度が大きい(鈍感?)だからできるのであって、あんまり借金を怖がらない人が多いが、ここは意識しないと、コロナのような不測の事態で1発退場である。
内部留保をためる
小さい会社は特に意識することが、内部留保をためること。内部留保をためるには、しっかり税金を払うしかない。内部留保をためることを意識すれば、意味のない節税はしないよねって話。
①社宅、②非常勤役員、③小規模企業共済、④退職金控除、⑤日当手当の設定くらいじゃないかな。王道でやっていい節税は。それ以外は、例えば保険の節税なんて、税金の繰り越しだし、あとで結局税金払う必要があり、かつ節税時にキャッシュが出ていくのであんまり意味はないと思っている。
自己資本比率50%以上
自己資本比率は、資産に対する純資産の割合である。例えば、資産100万・負債60万・純資産40万の場合は、自己資本比率は40%である。
起業時点は、資本金が少額の場合は、負債の割合が大きくなるので自己資本比率は20%くらいなるだろう。自社も自己資本比率は20%ほど。ただし、実質無借金であるなら、自己資本比率が低くてもそこは初期だから別に落ち込む必要はない。
内部留保をしっかり残して自己資本比率を上げていくのが強い会社。純資産の割合の中で投資を行ってコツコツ黒字をためて、自己資本比率をあげていく。
今回のコロナショックは、自己資本比率が低い会社が厳しくなる。コロナをきっかけにより一層自己資本比率を上げていく意識は高まった。
持続可能な会社
会社を経営していくと、周りと比較して落ち込んだり、焦ったりするときがある。周りとの比較は、いい面も悪い面もある。かなり大規模な投資をしていたり、素晴らしい事務所を構えていたり、人材を多く採用していたりするのを見て、劣等感を抱き、焦りから間違った判断をし兼ねない。
ここで大事なのは、前提条件がそれぞれ違うのである。前提条件が違うのに同じスピードを真似るのは、思考停止である。ロジックで経営をする必要がある。
他にもスタッフのモチベーションを上げることにフォーカスしないこと。モチベーションを上げるために給与の割合を上げて会社の内部留保をできない状況まで上げるのは、短期的には良いけど、長期的には?である。コロナで会社を倒産してしまっては、長い目でみたらスタッフへの給料の総額は減っているのである。
モチベーションは良い日もあれば、悪い日もある。なので、あんまりモチベーションを意識しないことが大切である。
持続可能な会社を創るには?という判断基準で会社を経営してくことが大事である。フリーランスは短期的には、給料の総額は大きくなるが、長期的には?であるように。
持続可能かどうかを判断基準に経営していこう!まだまだ道のりは長いし、生き残ればチャンスは何度でも来る。これは自分のこれからの長い経営人生の指針にしたい。
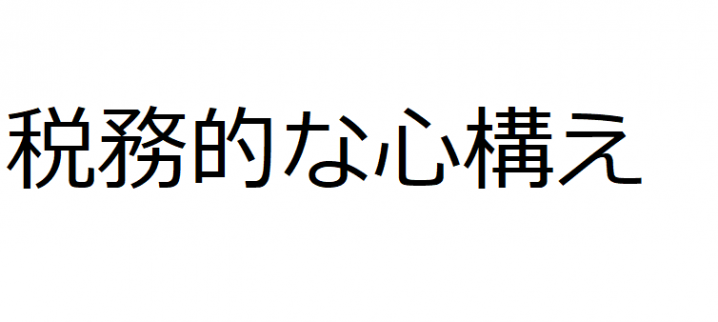

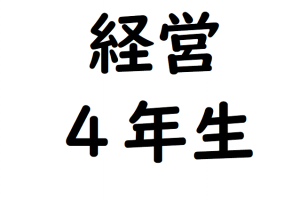
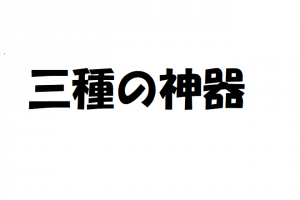
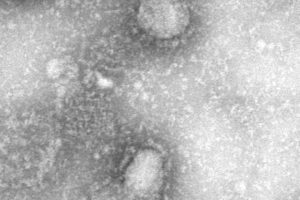
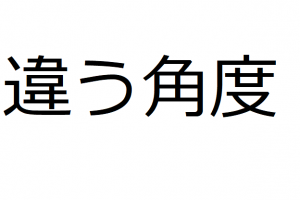
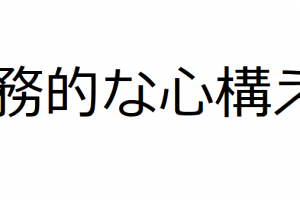
コメントを残す